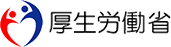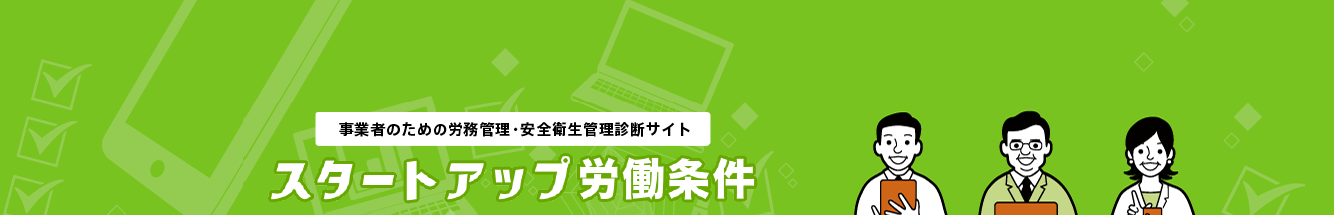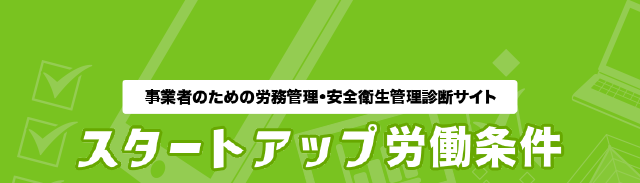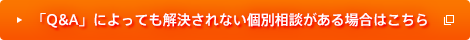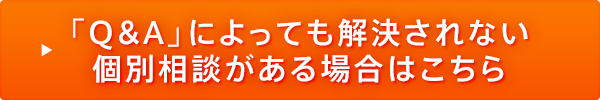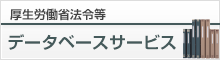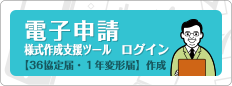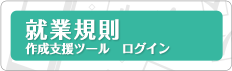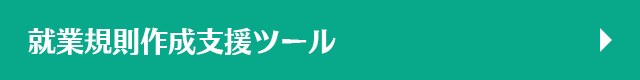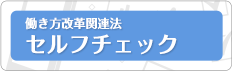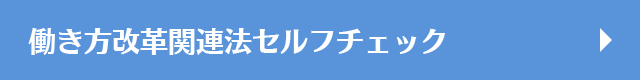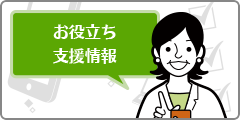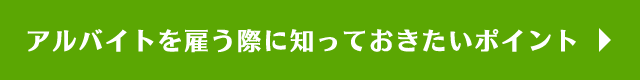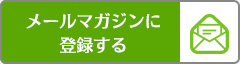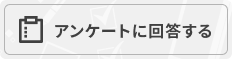解雇・雇止め
定年後の65歳までの継続雇用の期間の労働条件はどうなるのですか。
定年の年齢は60歳を下回ることができません(高年法8)し、これに反する定年の定めは無効となります。また、2004年(平成16年)高年法改正により、65歳未満の定年を定めている事業主は65歳までの高年齢者の雇用の確保のため、①定年年齢の引き上げ、②継続雇用制度の導入、③定年の廃止のいずれかの措置をとる必要があると定められました(9条①)。ここでいう「継続雇用制度」とは、「現に雇用する高年齢者が希望するときには、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度」のことで、ここには子会社等への転籍なども含まれます)。
この継続雇用制度における労働条件は、「継続」雇用だからといって、定年前のものがそのまま維持されるとは限りません。定年後の継続雇用制度が就業規則等に規定され、そこに定年後の継続雇用の下での労働条件が記載されていて、その就業規則が周知されている場合には、その就業規則内容が合理性を持つ限り、定年後継続雇用期間における労働条件はそれによることになります。そのほか、定年後継続雇用期間における労働条件を個別合意によって定める場合もありますが、それでも違法ではありません。
では、定年後継続雇用の条件について労働者と使用者が合意に至らなかった場合にはどうなるでしょうか。この場合について、厚生労働省「高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)」Q1-9には、「事業主の合理的な裁量の範囲の条件を提示していれば、労働者と事業主との間で労働条件等についての合意が得られず、結果的に労働者が継続雇用されることを拒否したとしても、高年齢者雇用安定法違反となるものではありません。」とありますので、継続雇用後の労働条件の合意ができずに結果として継続雇用の契約が締結できなかったとしても高年法違反とはならないと考えられています。ただし、「事業主の合理的な裁量の範囲の条件を提示していれば」という限定付きですので、「合理的裁量の範囲」を逸脱した条件を示した結果継続雇用ができなかった場合には不法行為として損害賠償責任が発生することもあります(トヨタ自動車事件、名古屋高判平成28年9月28日、九州総菜事件、福岡高判平成29年9月28日)。
高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/
ですから、継続雇用となる場合に、あまりに従来の職種と異なったり、あまりに賃金が低下するような場合には適切な継続雇用ではないと判断されることがあります。さらに、継続雇用が有期雇用であるとか短時間雇用である場合、通常の労働者との間で業務の内容等による「不合理な待遇の禁止」(パート有期法8条)が適用されますので、この点からも問題となることがあります。