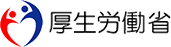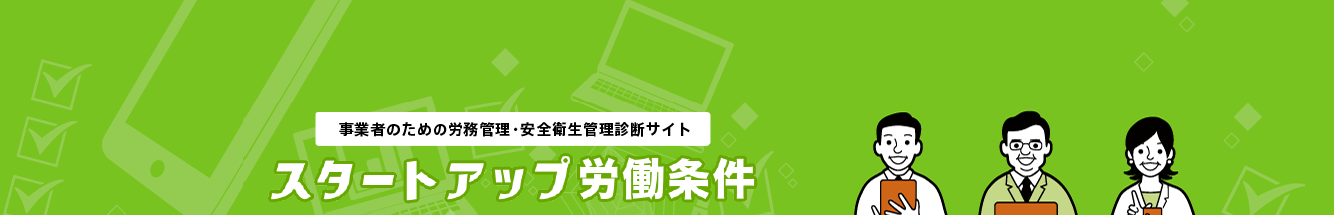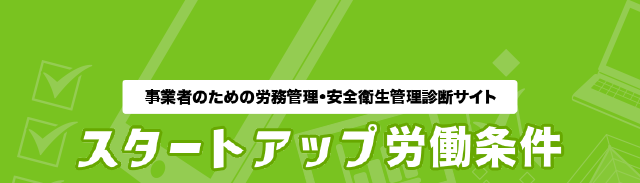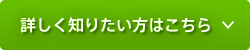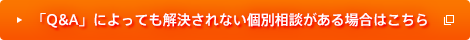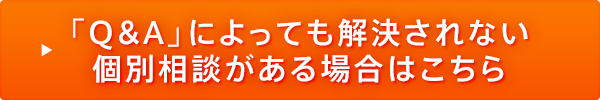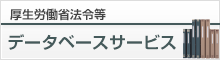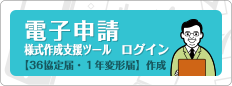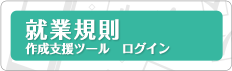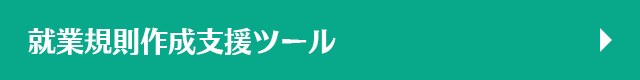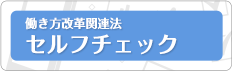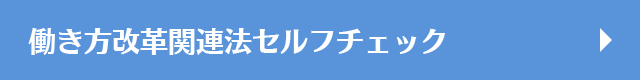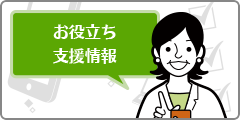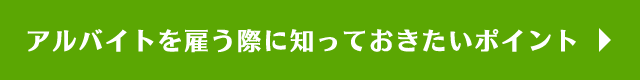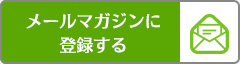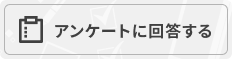雇用契約
面接のとき、残業時間は実際どのくらいですかとよく聞かれます。どの程度答えればよいでしょうか?
(1)労働条件等の明示と労働時間関係の明示事項
労働者の募集を行う企業は、募集に応じて労働者になろうとする者に対し、その者が「従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件」(以下「従事すべき業務の内容等」といいます。)を明示しなければなりません(職安法5の3①)。
この「従事すべき業務の内容等」のうち労働時間関係の明示事項は、「始業・終業の時刻、所定時間外労働の有無、休憩時間、休日に関する事項」です(職安法施行規則4の2③)。
(2)労働条件の明示等についての留意点
厚労省は、労働者の募集を行う際の労働条件の明示等について、留意点をまとめたリーフレットを作成し、その周知に努めています。その中で、労働条件等の明示について記載例を示しています。
時間外労働に係る記載例については、「あり(月平均20時間)」としており、時間外労働の有無だけでなく、ある場合には、具体的に理解されるよう時間外労働時間数を月平均で示しています。
(3)面接時に残業時間の実際を聞かれた場合
以上から、面接のときに残業時間の実際を聞かれた場合には、募集に応じて労働者になろうとする者は、労働者の募集を行う企業が明示した業務内容の仕事に応募しているわけですから、当該企業の従業員全体の平均残業時間ではなく、その募集対象の業務に従事されている労働者の実際の残業時間を月平均で示すなどの対応が望ましいと考えます。
なお、月平均の残業時間に加え、当該募集対象の業務に従事されている労働者のうち一日と一月の残業時間が最も長い者の時間を示すことも考えられます。
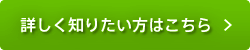
募集内容の的確な表示等
また、新聞等に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法(※)により労働者の募集を行う者は、「従事すべき業務の内容等」を明示するに当たっては、労働者の適切な職業選択に資するため、当該募集に応じようとする労働者に誤解を生じさせることのないように平易な表現を用いる等その的確な表示に努めなければなりません(職安法5の4①)
※厚生労働省令で定める方法
書面の交付、ファクシミリによる送信、電子メール等の送信、有線放送又は自動公衆送信装置その他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法(職安法施行規則4の3)
労働者の募集を行う者が適切に対処するために必要な事項
必要な事項について、厚労省が指針(平成11年労働省告示141号)を示しています。「従事する業務の内容等」を明示するに当たっては、次の事項などが指針に示されています。
- ①可能な限り速やかに明示しなければならないこと。
- ②次に掲げるところによらなければならないこと。
- ア 虚偽又は誇大な内容としないこと。
- イ 労働時間に関しては、始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日等について明示すること。
- ③次に掲げるところによるべきであること。
- ア 原則として、募集に応じて労働者になろうとする者等と最初に接触する時点までに労働条件を明示すること。
- イ 「従事すべき業務の内容等」の事項の一部をやむを得ず別途明示することとするときは、その旨を併せて明示すること。
- ④次に掲げる事項に配慮すること。
- ア 募集に応じて労働者になろうとする者等に具体的に理解されるものとなるよう、「従事すべき業務の内容等」の水準、範囲等を可能な限り限定すること。
- イ 従事すべき業務の内容に関しては、職場環境を含め、可能な限り具体的かつ詳細に明示すること。
- ウ 明示する「従事すべき業務の内容等」が労働契約締結時の労働条件と異なることとなる可能性がある場合は、その旨を併せて明示するとともに、労働条件が既に明示した内容と異なることとなった場合には、速やかに知らせること。
求人申込書など
- (1)求人申込書における時間外労働に係る記載
厚労省は、求人事業主に対し、求人申込書の書き方のポイントを示しています。 ポイントには、①労働条件などの明示は、労働者が職場に適応してその能力を有効に発揮するためにも、就職後のトラブルを避ける上からも重要であること、②労働条件はそのまま採用後の労働条件になることが期待されていること、求職者から誤解を生じにくいかたちで、正確かつわかりやすく記載すること、③ハローワークの窓口ではわかりやすい記載方法のアドバイスを行っていることなどが示されています。
求人申込書の労働時間に係る記載事項中「時間外労働」に関しては、
①「時間外労働【あり】の場合は、月平均残業時間数を記入して下さい。」、
②「特別条項付きの36協定を締結している場合は「あり」を選択し、「特別な事情・期間等」欄に特別な事情や延長時間などについて具体的に記入してください。例:「○○のとき(特別な事情)は、1日○時間まで、○回を限度として1ヶ月○時間まで、年に○時間できる」」
と書き方のポイントを示しています。
なお、厚労省では、ハローワークにおける求人票の記載内容と実際の労働条件の相違に係る申出等の件数を公表しています。求人条件と実際の労働条件が異なるといった相談等があった場合については、全国のハローワークにおいて事実確認と必要な是正指導を行うほか、法違反のおそれなどがある場合には、当該求人の職業紹介の一時保留や求人の取消が行われる場合があります。相談を受けるための「ハローワーク求人ほっとライン」も開設されています。 - (2)各種認定制度における労働時間に係る認定基準
厚労省は、働きやすい職場づくりに実績を上げている企業を認定していますが、認定する場合の基準として、労働時間の状況についての実績を求めています。
①若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定」の基準
「前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下かつ、月平均の法定時間外労働60時間以上の正社員が1人もいないこと。」
②女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」の基準
「雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の各月ごとに全て45時間未満であること。」
③次世代育成支援対策法に基づく「くるみん認定」の基準
「計画期間の終了日の属する事業年度において次の(1)と(2)のいずれも満たしていること。(1)フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること。(2)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと。」
労働者の募集を行う者が適切に対処するために必要な事項
労働条件等の明示及び募集内容の的確な表示については、次の指針の中で適切に対処するための事項が示されています。
平成11年労働省告示141号
指針名「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針」(最終改正
令和4年厚生労働省告示第143号)