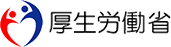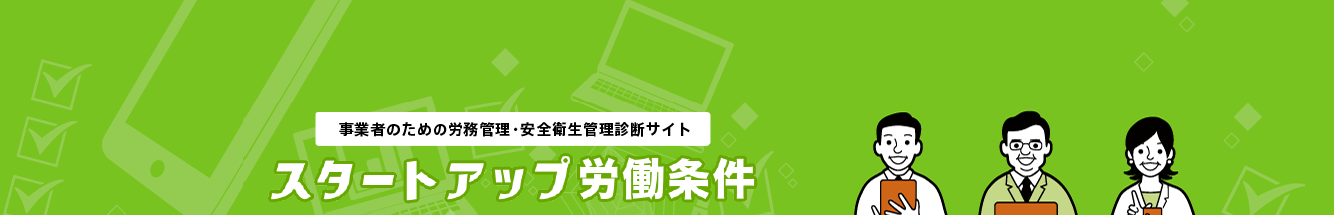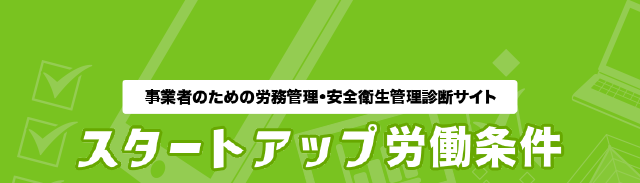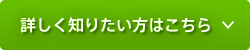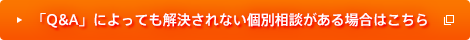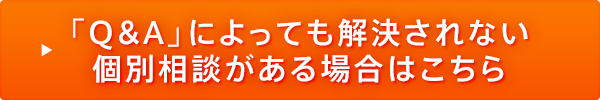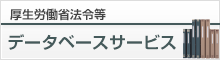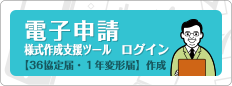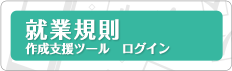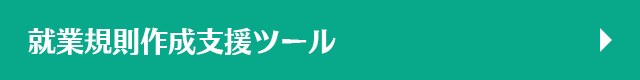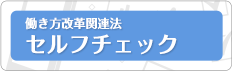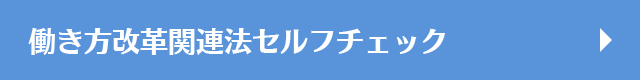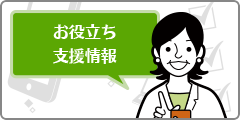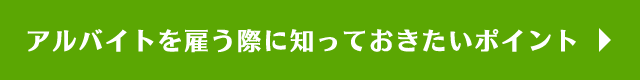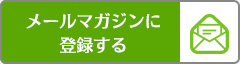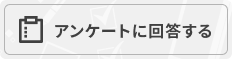雇用契約
内定や内々定を取り消す時また、内定や内々定を辞退された時は、どのような点に留意すればよいのでしょうか?
採用内定とは、「労働者と使用者との間で一定の始期及び採用内定通知書又は誓約書に記載されている採用内定取消事由が生じた場合は解約できるという解約権留保を付して労働契約を締結した状態」を指すことが多いものと考えられます。
採用の内々定とは、採用内定状態までには至らないものの、お互いがその状態を尊重して、採用内定に至るように信義則上努力すべき状態を言います。
採用内定の状態において、既に、労働者と使用者との間に一定の労働契約が成立しているのであれば、使用者の内定の取消、または、労働者からの内定の辞退は、一方的な契約破棄になります。内定取消の場合には、実質は解雇としての合理的な理由が必要です(労契法16)。労働者側からの内定辞退も、それが合理的な理由が認められないのであれば損害を賠償しなければならない場合も考えられます。
採用の内々定は、内定の段階に比べて多くの場合に労働契約を締結したとの認識には至っていないと考えられます。そのため、内々定の取消は解雇ではなく、また、内々定の辞退も契約の破棄ではないとも考えられますが、個別の事案によっては、拘束関係の度合いが強ければ「採用内定」と認められ、労働契約が成立していると判断されることもあり得るほか、労働契約は成立していない場合でも、採用内定の「予約」とされることにより、内々定の取消や辞退が信義に反し、相手方の期待権を侵害するものとして損害賠償責任が認められることもあり得ます。
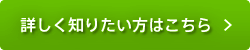
採用内定
採用内定の法的性格は事案により異なりますが、 採用内定通知のほかには労働契約締結のため特段の意思表示をすることが予定されていない場合には、採用内定により、始期付、採用内定取消事由に基づく解約権留保付労働契約が成立したと認められることが多いと考えられています。そのため、採用内定取消は解雇に当たり、労契法16条の解雇権の濫用についての規定が適用され、「客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合」には、権利を濫用したものとして解雇(採用内定取消)は無効となります。
解雇としての合理的な理由
採用内定取消が有効とされるのは、原則的には
- ①採用内定の取消事由が、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であること、
- ②この事実を理由として採用内定を取消すことが、解約権留保の趣旨、目的に照らして、解雇として客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができる場合(大日本印刷事件 最判昭54,7,20)
に限られると考えられます。
上記①の事由について、具体的には、ⅰ契約の前提となる条件や資格の要件を満たさないとき、ⅱ健康状態の悪化、ⅲ重要な経歴詐称、ⅳ重要な必要書類を提出しないこと、ⅴその他の不適格事由などが考えられます。
さらに、経営状況の悪化による採用内定取消も考えられます。この場合については、基本的に整理解雇の場合に準じ、いわゆる整理解雇の4要素、すなわち①人員整理の必要性、②解雇回避の努力義務、③解雇対象者の選定の合理性、④手続の妥当性、を踏まえて、その有効性が判断されることになると考えられます。
採用の内々定
採用の内々定とは、内定の段階に比べて多くの場合に労働契約を締結したとの認識には至っていないと考えられます。そのため、内々定の取消は解雇ではなく、また、内々定の辞退は契約の破棄ではないとも考えられますが、個別の事案によっては、拘束関係の度合いが強ければ、「採用内定」と認められ、労働契約が成立していると判断されることもあり得るほか、労働契約は成立していない場合でも、採用内定の「予約」とされることにより、使用者側で合理的な理由なく、内々定を破棄すれば、期待権を侵害したものとして、学生や労働者側から損害賠償責任を問われることもあり得ます。
内々定の取消
個別の事案によって、拘束関係の度合いによっては「採用内定」と認められることもあり得ますので、その場合には当該内々定取消の適法性は司法において判断されることとなります。
学生・労働者側からの内定辞退
内定取消は使用者側の行為ですが、内定辞退は学生・労働者側からの行為になります。内定の段階ですでに労働契約は成立していると認められる場合には、学生・労働者側からする一方的な破棄は契約違反になりかねず、事由によっては損害賠償責任が課される場合があります。しかし、労働者の意思に反して労働契約の履行を義務づけることはできないため、損害賠償責任に止まります。
学生・労働者側からの内々定の辞退
学生・労働者が内々定を辞退する場合には職業選択の自由(憲法22条1項)もあるために、原則として内々定の辞退が違法になるということは考えにくいところです。
行政による規制
- ①採用内定についての労基法の適用
採用内定によって労働契約が成立していると認められれば、採用内定取消が解雇とみなされ、解雇予告等について規定する労基法20の解雇予告の規定が適用される場合があります(※)。
(※)採用内定者は、いまだ具体的な就労義務を負うことなく、賃金も支払われていないということから、労基法の適用を否定する裁判例もあります。 - ②ハローワークによる指導
新規学卒者の採用内定取消を行う企業は所定の様式により、所轄のハローワークに通知する(職安則35条②)こととされており、この通知を受けてハローワークにおいては、労働者の雇入方法の改善等のため、企業に対して指導を行うとともに、採用内定取消の内容が一定の場合(※)に該当するときは、学生生徒等の適切な職業選択に資するため、その内容を公表することができることとされています (職安則17条の4、「職業安定法施行規則第十七条の四第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める場合」(平成21年厚生労働省告示第5号))。- (※)・2年度以上連続して行われたもの
- ・同一年度内において10名以上の者に対して行われたもの
(内定取消しの対象となった新規学卒者の安定した雇用を確保するための措置を講じ、これらの者の安定した雇用を速やかに確保した場合を除く。) - ・事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められないときに、行われたもの
- ・内定取消しの対象となった新規学卒者に対して、内定取消しを行わざるを得ない理由について十分な説明を行わなかったとき
- ・内定取消しの対象となった新規学卒者の就職先の確保に向けた支援を行わなかったとき
- ●裁判例
- ①大日本印刷採用内定取消事件(昭54.7.20最二小判)
要旨 採用内定の取消事由は、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られると解するのが相当である。
https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/00173.html - ②日本電信電話公社事件(昭48.10.29大阪高判)
要旨① 本件採用内定取消当時には、いまだ右始期は到来していなかったのであって、公社と被控訴人との間には具体的な労働契約上の法律関係は発生していないのであるから、労基法の立法精神が、もっぱら労働契約上の法律関係の存在を前提とし、そこにおける信条を理由とする均等待遇の原則を規定しているものである以上、労基法第3条の適用(同条にいう「労働条件」には「労働契約の締結」は含まれない)はこれを否定すべきである。
要旨② 採用内定者である被控訴人はいまだ具体的な就労義務を負うことなく、賃金も支払われていないのであるから、労基法の適用は受けないものである。
https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/00166.html - ③インフォミックス事件(平9.10.31東京地決)
要旨 採用内定者は、現実には就労していないものの、当該労働契約に拘束され、他に就職することができない地位に置かれているのであるから、企業が経営の悪化等を理由に留保解約権の行使(採用内定取消)をする場合には、いわゆる整理解雇の有効性の判断に関する〔1〕人員削減の必要性、〔2〕人員削減の手段として整理解雇することの必要性、〔3〕被解雇者選定の合理性、〔4〕手続の妥当性という四要素を総合考慮のうえ、解約留保権の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当と是認することができるかどうかを判断すべきである。
https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/06985.html