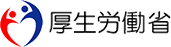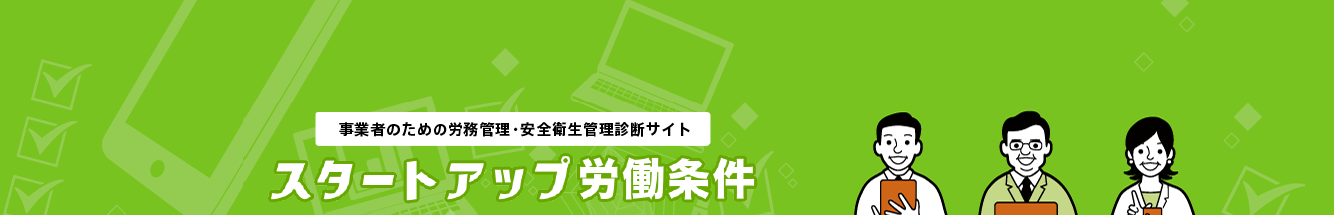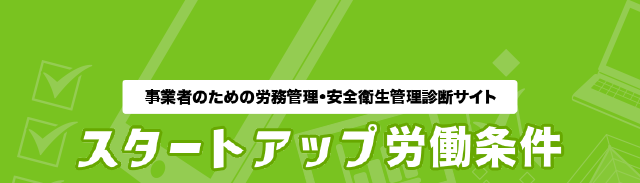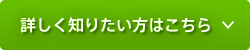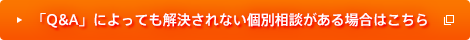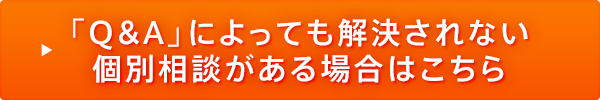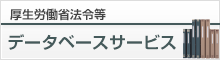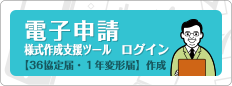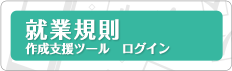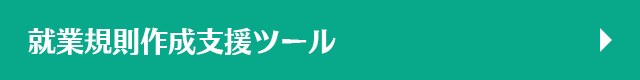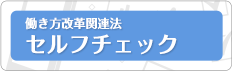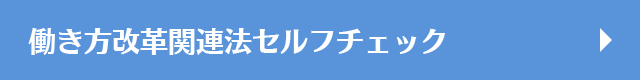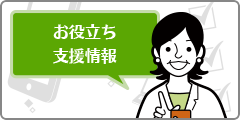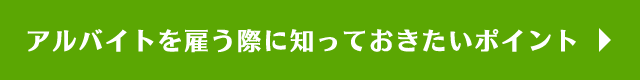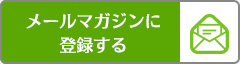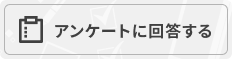労働時間・休日・休憩
システムエンジニアについて専門業務型裁量労働制を採用したいと考えています。どう進めればよいでしょうか?
労働基準法第38条の3による「専門業務型裁量労働制」とは、業務の性質上、その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量に委ねる必要があるため、業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして定められた20の業務の中から、対象となる業務等を労使協定で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使協定であらかじめ定めた時間労働したものとみなす制度です。
専門業務型裁量労働制を導入するには、次の手順で進めることが必要です。
- ・労使協定を過半数労働組合又は過半数代表者と結ぶ
- ・個別の労働契約や就業規則等を整備する
- ・所轄労働基準監督署に協定届を届け出る
- ・労働者本人の同意を得る (令和6年4月1日から必要になった事項)
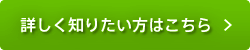
専門業務型裁量労働制の対象業務
- 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
- 情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であってプログラムの設計の基本となるものをいう。7において同じ。)の分析又は設計の業務
- 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第28号に規定する放送番組(以下「放送番組」という。)の制作のための取材若しくは編集の業務
- 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
- 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
- 広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務)
- 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)
- 建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)
- ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
- 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)
- 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)
- 銀行又は証券会社における顧客の合併及び買収に関する調査又は分析及びこれに基づく合併及び買収に関する考案及び助言の業務(いわゆるM&Aアドバイザーの業務)
- 公認会計士の業務
- 弁護士の業務
- 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
- 不動産鑑定士の業務
- 弁理士の業務
- 税理士の業務
- 中小企業診断士の業務
※太字部分は令和6年4月1日から追加される業務です。
20の業務のなかには「情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であってプログラムの設計の基本となるものをいう)の分析又は設計の業務」と「事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)」があります。これらの業務に該当する場合は、専門業務型裁量労働制の導入が可能となります。
専門業務型裁量労働制の導入の流れは以下のとおりです
-
1 労使協定を過半数労働組合又は過半数代表者と結ぶ
【労使協定で定めなければならない事項】
- ① 制度の対象とする業務(省令・告示により定められた20業務)
- ② 1日の労働時間としてみなす時間(みなし労働時間)
- ③ 対象業務の遂行の手段や時間配分の決定等に関し、使用者が適用労働者に具体的な指示をしないこと
- ④ 適用労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉確保措置の具体的内容
- ⑤ 適用労働者からの苦情処理のために実施する措置の具体的内容
- ⑥ 制度の適用に当たって労働者本人の同意を得なければならないこと
- ⑦ 制度の適用に労働者が同意をしなかった場合に不利益な取扱いをしてはならないこと
- ⑧ 制度の適用に関する同意の撤回の手続
- ⑨ 労使協定の有効期間(※3年以内とすることが望ましい)
- ⑩ 労働時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況、苦情処理措置の実施状況、同意及び同意の撤回の労働者ごとの記録を協定の有効期間中及びその期間満了後3年間保存すること
※下線部分は、令和6年4月1日以降、労働者に専門業務型裁量労働制を適用させるために追加で必要となる事項です。既に協定を締結している場合、改めて協定をし直す必要があります。
- 2ー① 個別の労働契約や就業規則等を整備 (繰り返しの整備は不要)
- 2-② 所轄労働基準監督署に協定届を届け出る
- 3 労働者本人の同意を得る (令和6年4月1日から必要になる事項)
-
4 制度を実施する
「みなし労働時間」労働したものとみなされる。
【運用の過程で必要なこと】
- ① 対象業務の遂行の手段や時間配分の決定等に関し、使用者が適用労働者に具体的な指示をしないこと
- ② 対象業務の内容等を踏まえて適切な水準のみなし労働時間を設定し、手当や基本給など相応の処遇を確保すること
- ③ 適用労働者の健康・福祉確保措置を実施すること
- ④ 適用労働者からの苦情処理措置を実施すること
- ⑤ 同意をしなかった労働者や同意を撤回した労働者に不利益な取扱いをしないこと
- ⑥ 労働時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況、苦情処理措置の実施状況、同意および同意の撤回の労働者ごとの記録を協定の有効期間中及びその期間満了後3年間保存すること
- 5 労使協定の有効期間の満了 (継続する場合は1へ)
「専門業務型裁量労働制について」
https://www.mhlw.go.jp/content/001164346.pdf