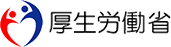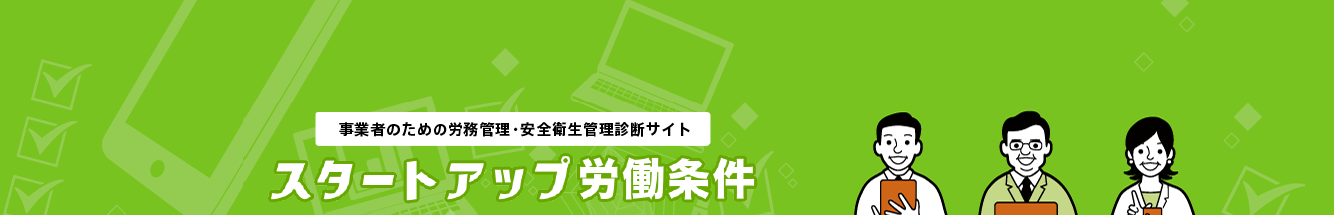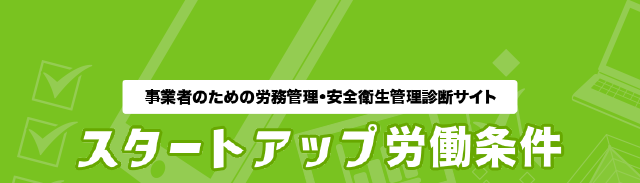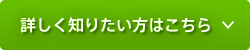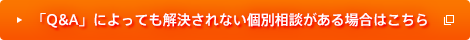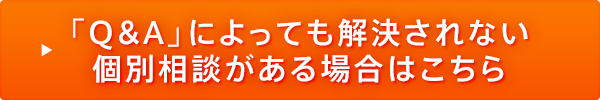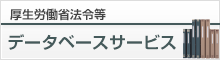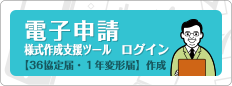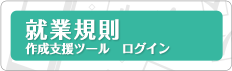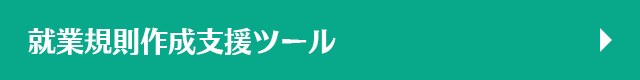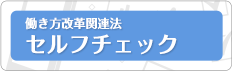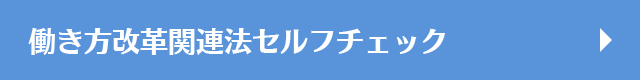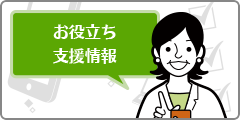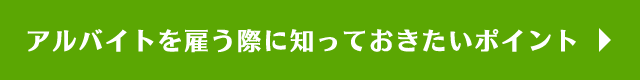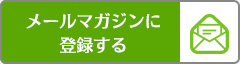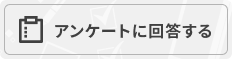その他
社内預金を、市中金利より高い利率で運転資金として利用すれば、従業員のためにもなると思うのですが、問題あるのでしょうか?
労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、または貯蓄金を管理する契約を行うことが禁止されていますが、労働者が任意に貯蓄金の管理を使用者に委託する場合には、労使協定の締結・届出、貯蓄金管理規程の作成、利子をつけること等一定の条件を満たすことにより、預金を受け入れる社内預金を行うことが認められています(労基法18)。
社内預金として預けられた資金は事業の運転資金等として活用されることがありますが、原資はあくまでも労働者の賃金であることから、預金の安全性の確保が最も重要な課題であり、保全措置を講ずること、利子は利率の最低限度である下限利率以上とすること、預金者一人当たりの預金額の限度を定めることなどが義務付けられています。
なお、預金額を毎月の賃金から控除する場合には、賃金控除に関する労使協定を締結する必要があります(労基法24条ただし書き)。
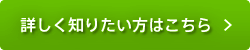
預金の保全
(1) 預金の保全
預金の保全については、毎年3月31日現在の受入預金額の全額について、その後の1年間を通じて一定の保全措置を講ずることとされています(賃確法3)。
その具体的内容は同法施行規則2条で以下のように定められ、労使協定においていずれの方法によるのか(複数を併用することも差し支えない)を明確にする必要があります。
- ①事業主(国及び地方公共団体を除く。以下同じ。)の労働者に対する預金の払戻しに係る債務を銀行その他の金融機関において保証することを約する契約(当該債務を、一般社団法人又は一般財団法人であって、債務の保証を業とするもののうち厚生労働大臣が指定する法人において保証することを約する契約を含む。)を締結すること。
- ②事業主の労働者に対する預金の払戻しに係る債務の額に相当する額につき、預金を行う労働者を受益者とする信託契約を信託会社又は信託業務を営む金融機関と締結すること。
- ③労働者の事業主に対する預金の払戻しに係る債権を被担保債権とする質権又は抵当権を設定すること。
- ④預金保全委員会を設置し、かつ、労働者の預金を貯蓄金管理勘定として経理することその他適当な措置を講ずること。
- ア 預金保全委員会の構成員の半数については、当該事業主に使用されている労働者であって、労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦を受けたものとすること。
- イ 預金保全委員会には次に定める事項を行わせること。
- a 事業主から労働者の預金の管理に関する状況について報告を受け、必要に応じ、事業主に対して当該預金の管理につき意見を述べること。
- b 労働者の預金の管理に関する苦情を処理すること。
- ウ 3月以内ごとに1回、定期に、及び預金保全委員会からの要求の都度、労働者の預金の管理に関する状況について預金保全委員会に対して書面により報告を行うこと。
- エ 預金保全委員会の開催の都度、遅滞なく、その議事の概要及び預金保全委員会に報告した労働者の預金の管理に関する状況の概要を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって労働者に周知させること。
- オ 預金保全委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを三年間保存すること。
預金保全委員会に併せて講ずる措置としては、実質的な保全機能を高めるために、貯蓄金管理勘定と支払準備金制度を併用することが望ましい(昭52.1.7基発4)。
(2) 保全措置を講じていない場合
保全措置を講じていない事業主に対しては、労働基準監督署長が文書により保全措置を講ずべき旨の命令を出すことができるとされています(賃確法4、同法施行規則3)。
また、保全措置が講じられていない事業場が倒産した場合の貯蓄金については、株式会社において、会社更生法が適用される場合は、更生手続開始前6月間の給料の総額に相当する額又はその預り金の額の3分の1に相当する額のいずれか多い額が共益債権として優先的に扱われます(会社更生法130)が、破産や民事再生の手続を採った場合には、優先度の低い債権として扱われることになります。
利子の下限利率
(1) 利子の下限利率
貯蓄金の管理が社内預金である場合の利率に関しては、法定の最低限度(下限利率)が利率省令(労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令)によって定められています。これを下回る利率を定めたり、あるいはまったく利率を定めなかった場合には、下限利率を定めたものとみなされます。下限利率は平成13年度以降年5厘とされています。
この下限利率は変動し得るものであることから、下限利率が引き上げられた結果、社内預金の利率が下限利率を下回ってしまうときは、下限利率を定めた利率省令の施行日までに、少なくともその下限利率と同率以上に引き上げる必要があります。
(2) 利子の計算方法
利子の計算方法は、利率省令6条において、利子は預入の月からつけること、10円未満の預金の端数には利子をつけることを要しないこと、利子の計算において円未満の端数が生ずるときは切り捨てることができること等が定められています。
したがって、年の途中から預け入れられたものについても、預け入れの月から年利に換算して下限利率以上となる月利の利子をつけなければなりません。
ただし、月の16日以降に預け入れられた金額についてはその月の利子をつけることを要せず、また、払戻しをした月については、払戻しの日の如何にかかわらず、その払戻金額についてその月の利子をつけることを要しません。
(3) 預金管理状況の報告
毎年3月31日以前1年間における預金の管理状況を、4月30日までに所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。