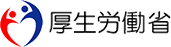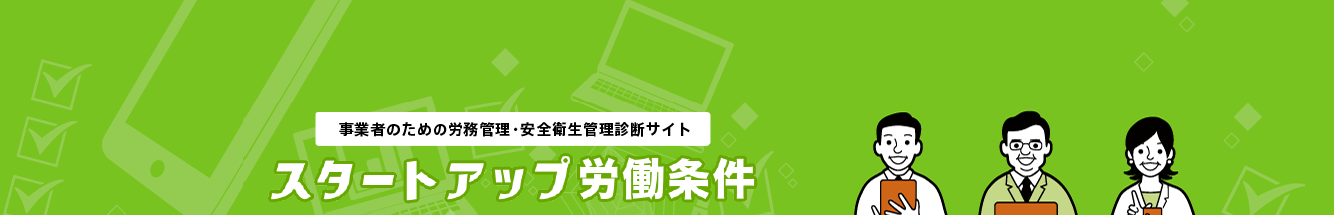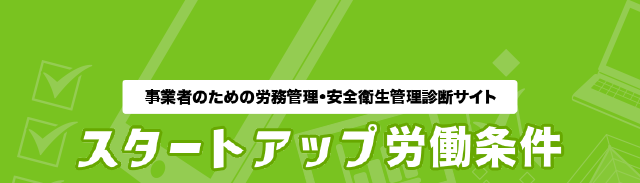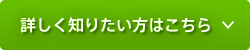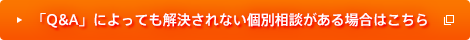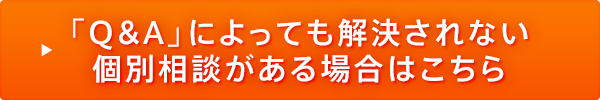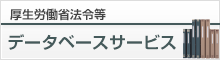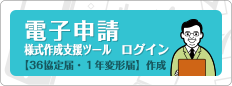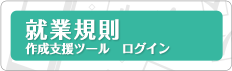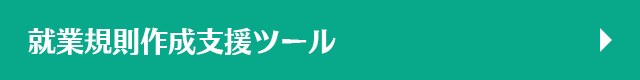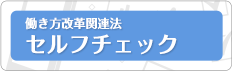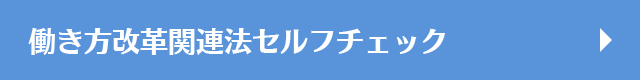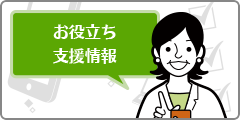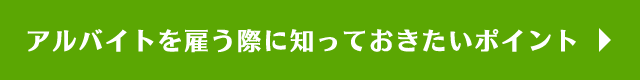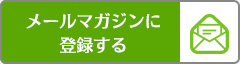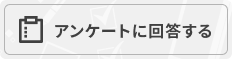就業規則・書類の保存
就業規則を変更するにあたり、労働者との協議が必要であるとのことですが、具体的に誰とどのような事項を協議する必要があるのでしょうか。
労働条件が就業規則によって決定されることは多いのですが(労契法7)、就業規則を労働者の不利益に変更したからといって、既に変更前の就業規則の定める労働条件で就労している労働者の労働条件に直ちに効力を及ぼすわけではありません。労働者と合意することなく、就業規則の変更によって労働者の不利益に労働条件を変更することはできないからです(労契法9本文)。
就業規則によって労働条件を労働者の不利益に変更する場合に、その変更がすでに雇用している労働者に対して拘束力を有するためには原則的には、その就業規則の変更に対する個々の労働者との合意が必要です(労契法9本文)。ただし、例外的に、その変更が、労働者に周知され、就業規則の変更が合理的なものである場合には、この変更に合意をしない労働者も拘束するとされています(労契法9ただし書、10)。この「合理的」であるかどうかは、①労働者の不利益の程度、②労働条件の変更の必要性、③変更後の就業規則の内容の相当性、④労働組合等との交渉の状況、⑤その他の就業規則の変更に係る事情、に照らして判断されます。
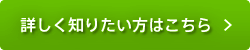
労働組合等との交渉の状況
「労働組合等との交渉の状況」にいう「労働組合等」には、労働者の過半数で組織する労働組合のみならず、少数派労働組合などその他の労働者団体も含まれています。この点について、「労働契約法の施行について」との通達(平成24年8月10日基発0810第2号)では、第3の4(3)オ(カ)に、「法第10条の『労働組合等との交渉の状況』の労働組合等には、労働者の過半数で組織する労働組合その他の多数労働組合や事業場の過半数を代表する労働者のほか、少数労働組合や、労働者で構成されその意思を代表する親睦団体等労働者の意思を代表するものが広く含まれるものであり、第四銀行事件最高裁判決で列挙されている「⑤労働組合等との交渉の経緯」「⑥他の労働組合又は他の従業員の対応」はこれに該当するものであること。」と記載されています。
また、労働組合がない場合には、過半数代表者に対する説明や過半数代表者の同意だけではなく、説明会を開催したり、労働条件を変更することの必要性やその効果などを説明するパンフレットを配布したりして労働者の納得を得るよう努力する必要もあります。
労働組合等との交渉事項
労働組合等との交渉事項としては、合理性をめぐる事項があげられますが、就業規則による労働条件の不利益変更にあたっては、これらについて真摯に交渉が行われる必要があります。合理性を判断する要素が上記のように①労働者の不利益の程度、②労働条件の変更の必要性、③変更後の就業規則の内容の相当性、④労働組合等との交渉の状況、⑤その他の就業規則の変更に係る事情ですので、これらの事項をめぐって、十分に交渉をする必要があります。不利益変更を根拠づける資料、例えば決算数字など経営状況を示す資料や変更前の労働条件と変更後の労働条件の比較を示す資料などを示す必要がある場面も生ずるでしょう。さらに、協議の相手方が労働組合である場合、多数派労働組合である場合にはもちろん、たとえ少数派労働組合であっても、労働条件の不利益変更について使用者が団体交渉を拒否したり、不誠実な態度(例えば、労働組合側の質問に対して返答をしない)で団交に臨んだ場合、不当労働行為(労組法7二)となる場合があります。