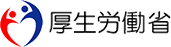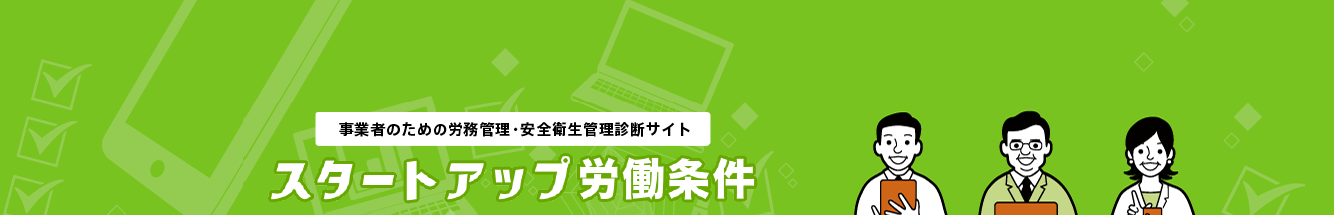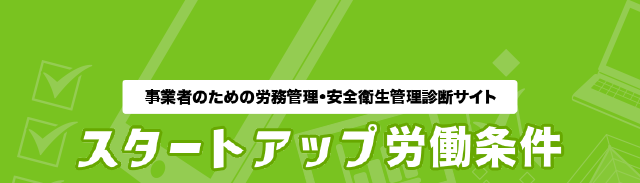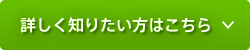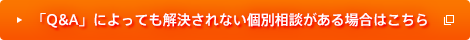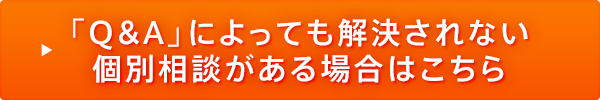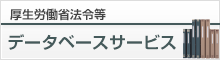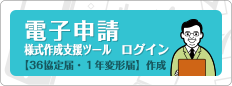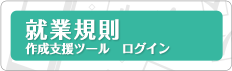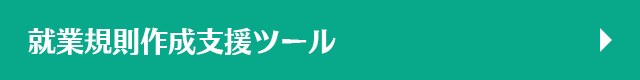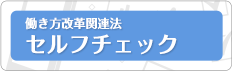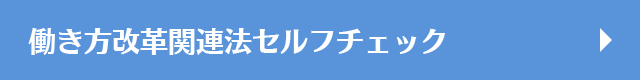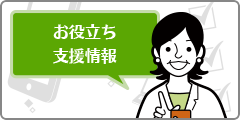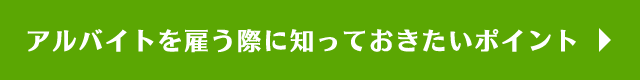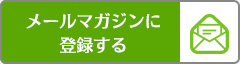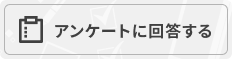年次有給休暇
年次有給休暇はどのような場合に、何日与えなければならないのでしょうか? また、どのような点に留意すればよいのでしょうか?
- (1)①入社から6か月間継続勤務し、②その期間の全労働日の8割以上出勤していれば、その労働者には10労働日の年次有給休暇を付与しなければなりません。また、その後1年間継続勤務し、その期間の出勤率が8割以上であれば、11労働日の年次有給休暇を付与することが必要です。以降も同様の要件を満たせば、表1の付与日数の年次有給休暇が発生します。
[表1 年次有給休暇の付与日数(一般の労働者)] 勤続年数 6か月 1年
6か月2年
6か月3年
6か月4年
6か月5年
6か月6年
6か月以上付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
また、所定労働日数の少ないパートタイム労働者であっても、表2の所定労働日数に応じて定められている日数の年次有給休暇を与えなければなりません。[表2 年次有給休暇の付与日数(週所定労働時間が30時間未満の労働者)] 週所定
労働日数年間所定
労働日数勤続年数 6か月 1年
6か月2年
6か月3年
6か月4年
6か月5年
6か月6年
6か月以上4日 169~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日 3日 121~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日 2日 73~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日 1日 48~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日 - (2)使用者は、年次有給休暇の付与に当たっては、次のような点に留意してください。
- ①年次有給休暇の利用目的によって、その取得を制限することはできません。
- ②労働者から年次有給休暇の請求があった場合には、原則としてこれを拒めません。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合には、これを他の時季に変更することができます。
- ③年次有給休暇の買い上げの予約をし、これに基づいて休暇の日数を減じたり、請求された日数を与えないことは法違反となるのでできません。
- ④使用者は、労働者が年次有給休暇を取得したことによって、労働者に対し賃金の減額その他の不利益な取り扱いをしないようにしなければなりません。(労基法附則136)
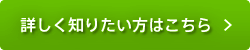
年次有給休暇の発生要件①―継続勤務
継続勤務は、在籍期間のことをいい、勤務の実態に即し、実質的に労働関係が継続しているかどうかによって判断されます。例えば、次のような場合でも、実質的に労働関係が継続しているといえる場合には、勤続年数を通算します(S63.3.14 基発150)。
- (1)定年退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合
- (2)臨時工が契約更新により6か月以上に及び、引き続き使用されている場合
- (3)在籍型の出向をした場合
- (4)休職後に復職した場合
- (5)臨時工、パート等を正社員に切り替えた場合
- (6)合併などで新会社に包括承継された場合 など
年次有給休暇の発生要件②―8割以上の出勤率
出勤率は、次の式で計算されます。
| 出勤率(%)= | 出勤した日 | ×100 |
| 全労働日 |
年次有給休暇が付与される要件としての出勤率の算定に当たって、全労働日と出勤日の取扱いは次によることとされています。
- (1)全労働日
次の日は全労働日から除外する日として取り扱われます。- ①使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日(H25.7.10基発0710第3号)
- ②労使いずれの責にも帰すべからざる不可抗力的事由による休業(H25.7.10基発0710第3号)
- ③争議行為としてのロックアウト期間
- ④正当なストライキその他の正当な争議行為により労務の提供が行われなかった日(H25.7.10基発0710第3号)
- ⑤所定休日に働いた日
- (2)出勤日
次の日は出勤日として取り扱われます。- ①遅刻又は早退した日
- ②業務上の傷病により療養のため休業した期間(労基法39⑧)
- ③育介法に規定する育児休業又は介護休業をした期間(労基法39⑧)
- ④産前産後休業(労基法39⑧)
- ⑤裁判所の判決により解雇が無効と確定した場合や、労働委員会による救済命令を受けて会社が解雇の取消しを行った場合の解雇日から復職日までの不就労日のように、労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日(H25.7.10基発0710第3号)
- ⑥年次有給休暇を取得した日(S22.9.13基発17)
- (3)労使間の決定するところによるもの
- ①就業規則で定められた慶弔休暇等
- ②生理休暇
〈関連判例〉
八千代交通事件(最高裁第一小法廷 平25.6.6判決)
【判例要旨】
労働者が解雇の無効を主張して提訴し、当該解雇の無効が確定して復職した事案において、年次有給休暇権の発生要件につき、無効な解雇期間中の不就労日は労基法39条1項及び2項における全労働日に含まれ、出勤日に算定しなければならないことが明らかにされた。
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/hanrei/yukyu/yukyu.html
事業の正常な運営を妨げる場合
年次有給休暇の取得日は労働者の権利ですから、原則として、労働者が好きな時季に年次有給休暇をとる日を指定することができます。ただし、労働者が指定した時季に休暇を与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合」には、使用者は、他の時季に変えてもらうこと(時季変更権)が認められています(労基法39⑤)。
使用者の時季変更権の行使が認められる「事業の正常な運営を妨げる場合」かどうかは、
個別的、具体的、客観的に判断されています(S23.7.27 基収2622)。裁判例では、労働者が所属する事業場を基準として、事業の規模、内容、労働者の担当する作業の内容、性質、作業の繁閑、代行者の配置の難易、労働慣行等諸般の事情を考慮して客観的に判断すべきものとされています。
使用者の年休5日付与義務
年次有給休暇の取得促進を目的に、2019年(平成31年)4月1日以降、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(パートタイム労働者や管理監督者も含まれます。)に対し、年休付与日から1年以内に5日の年休付与義務が使用者に課せられることとなりました(改正労基法39条7項参照)。同条違反に対しては、新たに罰則規定(30万円以下の罰金)も設けられており、使用者に対し年休5日の付与義務を強く課すものです。同義務が生じるのは当該年度ごとに10日以上の年休が新たに付与された場合であり、繰り越し分の日数を含めたものではありません。他方で、実際に取得した年休日数の算出(5日)については、前年度から繰り越された年休の取得日数も加味しうることとされています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
〈関連判例〉
此花電報電話局事件(最高裁第一小法廷 昭57.3.18判決)
【判例要旨】
年次有給休暇の成立要件に使用者の承認という観念をいれる余地はなく、特定の時季を指定した年次有給休暇の請求に対し、これを承認しまたは不承認とする旨の使用者の応答は、時季変更権を行使せずまたは行使する旨の意思表示をしたものに当ると解すべきである。
「事業の正常な運営を妨げる」か否かは当該労働者の所属する事業場を基準として、事業の規模、内容、当該労働者の担当する作業の内容、性質、作業の繁閑、代行者の配置の難易、労働慣行等諸般の事情を考慮して客観的に判断すべきである。
「交替服務者が休暇を請求する場合は、原則として前々日の勤務終了時までに請求する」旨の定めは、労働基準法39条に違反しない。
勤務開始時刻前に第三者(宿直職員)を介してなされた当日全日または午前中2時間の年次有給休暇の請求に対し、事業の正常な運営を妨げる虞があるとの判断の下に、休暇を必要とする事情いかんによっては右休暇を認めるのを妥当とする場合があると考え、休暇の理由をただしたところ、労働者が休暇の理由を明らかにすることを拒んだため、年次休暇の請求を不承認とする意思表示をしたことにつき、右の事情の下においては、不承認の意思表示が休暇期間の開始しまたは経過した後になされた場合であっても、適法な時季変更権の行使に当り有効と認めるのが相当である。
https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/03334.html
時事通信社事件(最高裁第三小法廷 平4.6.23判決、ID05935)
【判例要旨】
労働者が長期かつ連続した年次有給休暇を取得しようとするときは、事前の調整が必要であり、労働者が右の調整を経ることなく時季指定をしたときは、時季変更権の行使について使用者にある程度の裁量的判断の余地を認めざるを得ないが、右裁量的判断は合理的でなければならないところ、新聞記者の1か月の年休の時季指定について、後半部分についての時季変更権を行使したことは適法とされた事例。
https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/05931.html
不利益取扱いの禁止
労基法は、年次有給休暇をとった労働者に対して、使用者が賃金を減額したり、その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないことを定めています(労基法附則136)。
例えば、精皆勤手当や賞与を算定する際に、年次有給休暇を欠勤扱いにすることなどが不利益取扱いに当たります(S63.1.1 基発1)。
この規定は、年次有給休暇をとった労働者に対する不利益取扱いが年次有給休暇の取得を抑制し、労基法39条の精神に反することなどから、訓示規定として設けられたものです。労基法附則136条の違反は、直ちに罰則を伴うものではありませんが、労基署の是正指導の対象になりますし、また、精皆勤手当や賞与の減額などの程度によっては、公序良俗に反するものとして民事上無効(民法90)となる場合もあります。
〈関連判例〉
大瀬工業事件(横浜地裁 昭51.3.4判決、ID01445)
【判例要旨】
就業規則に定める皆勤手当制度、出勤奨励金制度において年次有給休暇で欠勤した日を通常の欠勤日として取り扱われ、当該手当を支給されなかった従業員が、その支払いを請求した事例で、皆勤手当等の諸手当の全部または一部を『年休を取得して休んだ日のあること」を理由にして支給しないことは違法と判断された。
https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/01445.html
沼津交通事件(最二小判 平5.6.25判決 ID06155)
【判例要旨】
乗務予定表作成後に年休を取得すると皆勤手当の全部または一部を控除する措置は、労基法の規定からして望ましいものではないものの、取得を抑制する趣旨ではなく実車率の向上を目的とするものであり、控除額の賃金に占める割合も小さく、取得実績や残日数を買い取っていたことなどからすれば、年休の取得を抑制し、権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものではなく、公序に反して無効とまではいえない。
https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/06155.html