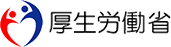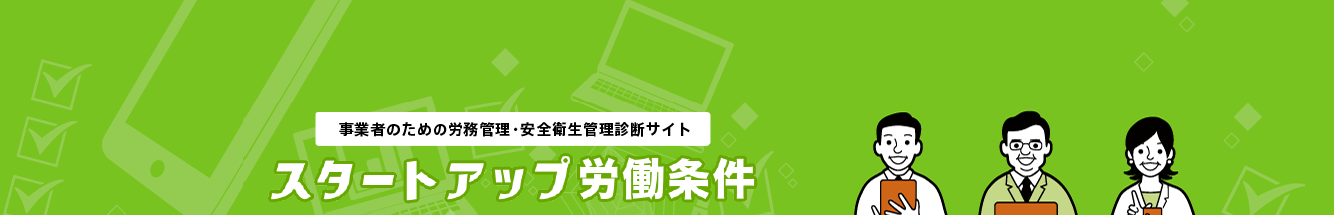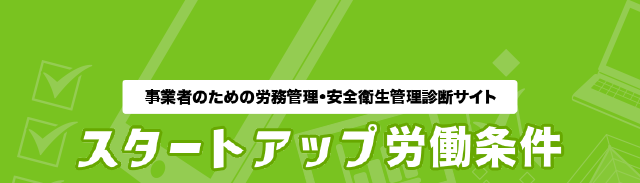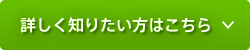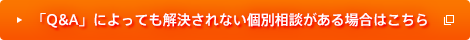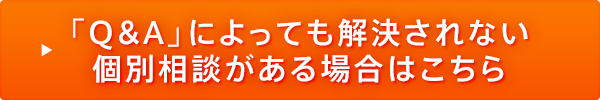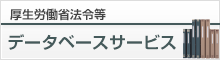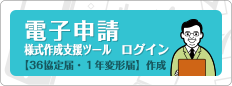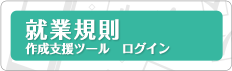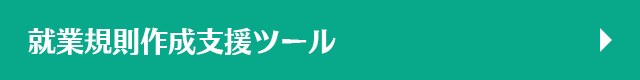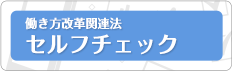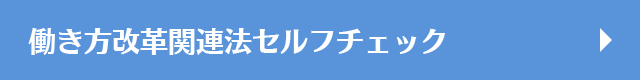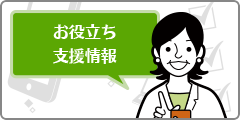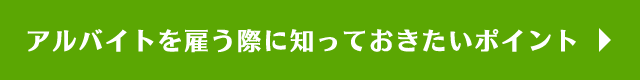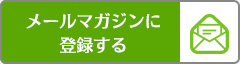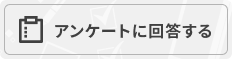年次有給休暇
年次有給休暇を積極的にとるよう従業員に促していますが、同僚へ負担がかかることや上司の目を気にしてなかなかとってくれません。もっととってもらうようにするにはどうすればよいのでしょうか?
年次有給休暇取得の促進策として、年次有給休暇を計画的に組み込んでとらせる『計画的付与』(計画年休)の制度があります。計画年休制度は、年次有給休暇日数のうちの5日を超える部分について、事業場で労使協定を結ぶことによって導入することができます。
労使でよく話し合い、効率的な年次有給休暇の取得に努めてください。
※この協定は、労働基準監督署へ届け出る必要はありません。
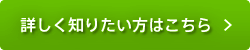
計画年休制度
計画年休制度は、労働者が自分の仕事との調整をしながら、気兼ねなく年次有給休暇をとれるようにするため、計画的に休暇の予定を組み込むものです。計画年休制度を導入するには、事業場で労使協定を結ぶ必要があります。計画的付与ができるのは、労働者が持っている年次有給休暇日数のうち、5日を超える部分についてであり、5日は労働者が好きな時にとれるように残しておかなければなりません(労基法39⑥)。
計画的付与の方法としては、例えば次のようなものがあります。
| (1)一斉付与方式…… | 事業場全体を休業にして一斉に休暇をとらせる。労使協定には、具体的な年次有給休暇日を定める。 |
| (2)班別の交替制付与方式…… | いくつかのグループ(班)に分け、班ごとに休暇をとらせる。労使協定には、班別に具体的な年次有給休暇日を定める。 |
| (3)個人別付与方式…… | 個々の労働者の希望を聞き、個人ごとに年次有給休暇計画表を作り、計画表で決めた日に休暇をとらせる。労使協定では、計画表を作成する時期や手続などを定める。 |
- (1)一斉付与方式
- ……事業場全体を休業にして一斉に休暇をとらせる。労使協定には、具体的な年次有給休暇日を定める。
- (2)班別の交替制付与方式
- ……いくつかのグループ(班)に分け、班ごとに休暇をとらせる。労使協定には、班別に具体的な年次有給休暇日を定める。
- (3)個人別付与方式
- ……個々の労働者の希望を聞き、個人ごとに年次有給休暇計画表を作り、計画表で決めた日に休暇をとらせる。労使協定では、計画表を作成する時期や手続などを定める。
(S63.01.01 基発1、H22.5.18 基発0518001)
なお、一斉付与方式や班別の交替制付与方式をとった場合に、年次有給休暇の残日数が5日に満たない労働者がいる場合には、年次有給休暇の付与日数自体を増やすことや特別な休暇を与えるなどの措置が必要です。
使用者の年休5日付与義務について
年次有給休暇の取得促進を目的に、2019年(平成31年)4月1日以降、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(パートタイム労働者や管理監督者も含まれます。)に対し、その年休付与日から1年以内に5日以上の年休付与義務が使用者に課せられることとなりました(労基法37⑦)。
年休付与日から1年以内に、使用者は労働者の意向を聴取した上で、使用者自ら時季指定を行い、5日の付与を行うことが義務づけられるものです。他方で労働者本人が自ら5日(半日単位で取得した年休も含まれます。)の年休を取得したり、計画年休をもって5日分の付与がなされた場合には、そもそも使用者の年休時季指定義務自体が消滅します。このため、以下のとおり、年休の取得促進策として、計画年休制度の導入や夏休み時期等の年休取得促進をもって、年休5日以上の取得を積極的に進めることが望まれます。
年次有給休暇の取得促進策
年次有給休暇の取得をためらう理由には、『みんなに迷惑がかかる」(73.3%)、「後で多忙になる」(43.5%)、「職場の雰囲気で取得しづらい」(30.2%)などが多く挙げられています(厚生労働省「労働時間等の設定の改善の促進を通じた仕事と生活の調和に関する意識調査」平成25年)。このため、それぞれの職場で、休暇の取得に対する意識改革や、休暇を取得しやすい職場づくりに、労使双方で取り組んでいくことが重要です。
「労働時間等見直しガイドライン」(H20.3.24 厚生労働省告示108)は、年次有給休暇を取得しやすい環境を整備するための方策を示しているので、そのポイントを挙げると次のとおりです。
- ●年次有給休暇管理簿の作成・周知
- ・使用者は年次有給休暇管理簿を作成・確認を行い、年次有給休暇の取得状況を労働者及び当該労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者に周知する。
- ・労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が、取得が進んでいない労働者に対して、業務の負担軽減を図る等労務管理上の工夫を行い、年次有給休暇の取得につなげるなど、年次有給休暇の取得促進に年次有給休管理簿を活用する。
- ●計画的な年次有給休暇取得
- ・労使間で1年間の仕事の繁閑や段取り及び当面達成すべき目標としての取得率の目安を話し合うこと。
- ・業務量の正確な把握、個人別年次有給休暇取得計画表の作成、年次有給休暇の完全取得に向けた取得率の目標設定の検討及び業務体制の整備、取得状況の把握
- ・年次有給休暇の計画的付与制度(労基法39⑥)の活用
-
●長期休暇の取得促進
- ・週休日と年次有給休暇とを組み合わせた2週間程度の連続した長期休暇
- ・取得時期の分散化
-
●年次有給休暇の取得促進
- ・時間単位年休の活用(労基法39④)
- ・半日単位の年次有給休暇の利用
◆労働時間等見直しガイドライン
労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)は、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号。以下「労働時間等設定改善法」という。)第4条第1項の規定に基づき、事業主のみなさまに労働時間等の見直しに向けて取り組んでいただくにあたり、参考としていただきたい事項を記載したものです。
なお、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)が成立し、労働時間等設定改善法及び労働基準法が改正され、勤務間インターバルを導入する努力義務や時間外労働の上限規制が新設されたことに伴い、「今後の労働時間法制等の在り方について(建議)」(平成27年2月13日労働政策審議会建議。)等も踏まえ、労働時間等見直しガイドラインも改正され、平成31年4月1日から適用されています。
その他の年次有給休暇の取得促進の手法
- (1)職場の意識改善のための取組み体制
- ・経営トップの主導による取組みへの意思表明、社内への呼びかけ
- ・管理職への教育、働きかけ
- ・人事労務管理部門、労働組合等関係者の連携
- ・従業員への呼びかけ、意識づけ
- (2)計画的な年次有給休暇取得
- ・個人別の年次有給休暇計画表の作成・共有化
- ・給与明細書等への年次有給休暇の残日数記載による注意喚起
- ・年次有給休暇の取得を組み入れた業務計画の策定
- ・取得状況のチェックとフォローアップ
- ・夏季・年末年始休暇に計画年休を充てて大型連休にする
- ・アニバーサリー(メモリアル)休暇(誕生日や結婚記念日などに休暇を充てる)
- (3)その他
- ・ブリッジ休暇(会社休日と祝日をつなげて連続休暇にする)
- ・未取得の年次有給休暇の積み立て など